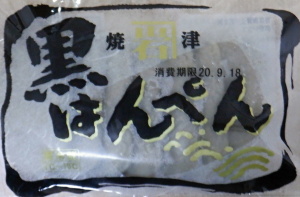つきまろでんせつ うきまろのゆめ-5 ― 2020年11月05日 18:30
郷里の友人から、だし道楽が届きました。最近では都内でも見かけるようになったみたいですが元々江田島の二反田醤油の製品です。今では、全国に知られているそうですが、お店は警固屋4丁目にあり、そこは嘗て、私が投げ釣りをした場所の近くであります。鍋桟橋といいましたが、今で言うバスターミナルでした。多くの人が行きかうところでしたが、時々釣りの合間に行ったりしました。昭和の50年代前半のことです。そんなことも随分と昔話ですし、当時海だったところはすっかり埋め立てられて団地になっていました。鍋桟橋とか言う人も今はいないでしょうし、小島と言う島も埋め立てられています。それでも10年前までは祖母もなんとか元気でしたので、その度にその跡地に行ったものです。そんな時代から私は、この本題でもある、スピンキャスティングリールが好きで使っていました。すべてが昭和です。そんな時代を、時々友人から送られてくるもので感じています。うどんと言えば、今現在は、大手チェーンのあの会社が目立ちますが、私が高校生まで普通のうどんと言えば呉の細うどんでした。それは、全国にあるものだと思っていたのですが、東京へ出てみるとそれはあり得ないことでした。もちろん、最初に食べたそのうどんに衝撃を覚えたことを記憶しています。それはまさにだし道楽とは無縁の汁でしたし、ネギももちろん違いました。麺もです。それも懐かしい昭和の思い出です。
さて、どうしようか・・・。再び息吹を行ないリセットですが、ここは単なる深呼吸の方がいいのかもしれません。なにせ相手は、ゆるゆるなのですからかえって精神統一などは逆効果なのかもしれません。いやいやそんなことはないと思い、関根バージョンになりつつあるいぶきを行います。雑念はどんどん浮かんできますので、それを排除するのは相当な精神統一が必要になってきました。
気を持ち直し、対策を考えました。しばし考えると、それでそこをイエローのスレッドで隠すことにしました。少し残念ではありますが、それは仕方ありません。対処できる方法でとなるとこうなりました。イエローの糸はNCPと呼ばれていた透けないタイプを使用しますが、それでも、旧グデブロッド社のサイズAという太さの細い糸を使うと、このような明るい色は、コーティングすると透けて見えがちです。よってその上の太さのCサイズの糸で巻くことにしました。するとまあ、何とかなりました。その画像です。ロッドクラフトと呼ばれる富士工業の本が出版されたのが昭和55年の3月3日と考えるとこのクラフトには必須であったGUDEBROD社のスレッド(巻糸)を知る人もかなり減ってきたのではないでしょうか。これも時代の流れの一つと捉えるしか無さそうです。
メタルスレッドと呼ばれる光沢糸の赤糸と黄色
イエローは透けるのを避け太さCで巻き、デザインしなおす
まあそれなりになんとかなるのかな
続いてエポキシコートに入ります。それには、2液性のエポキシコーティング剤を使用します。もちろんそこも妥協なしのいつもの材料を使うことにします。そこは、日ごろの作業とさほど変わりません。いつもの普通の流れです。何度かその2液性エポキシコートを重ねるとこのようになります。2液性のエポキシは多々ありますが、そこは、信頼性のおけるUSA製のものが良さそうです。それを国産で探すのはなかなか大変かと思います。これからビルディング/クラフトにトライされる方は、老舗中の老舗、フレックスコート社のものを選択すると良いかと思います。これは、その歴史の中で滅んでいないUSA製のエポキシコート剤です。そのバリエーションも多くあるのですが、スタンダードなものからトライされてはどうかと思います。慣れてきたら他のアイテムを使って頂くとより幅は拡がっていくと思います。
それから先もやはりいつもの作業になりますが、焦らずゆっくりと何度もが口癖です。それが、やはり一番の近道になると思います。自分用だから汚くても良いと考える方も多いかもしれませんが、それでもできるだけ綺麗に仕上がった方が愛着も湧いてくるのではないかと思いますので、是非諦めないで製作をしてみてください。少し残念ではありますが、このブログはクラフト、ビルディングの手順を解説したものではありませんので、何卒ご容赦の程宜しくお願い致します。
うきまろの「う」の字がうっかり剥がれるが、それは致し方ないところである。「月竿」のロゴも入れるとそれは、“つきまろッド”に変身なのだろうか?はたして?
最強アブマチック?
つきまろでんせつ うきまろのゆめ-6 ― 2020年11月09日 15:54
その変身ぶりは、仮面ライダー並みなのだろうか
本郷猛から、1号ライダーへ1971年から2020
コーティングを重ねて、仕上げに入りました。
ガイドも設定し直して、随分竿らしくなりました。これが案外大変なものです。ガイドの内径が揃っている訳ではないのです。しかも案外これが高額になります。それは最初から覚悟の上ですが、もしどなたかおれもやってみたいということになれば、本体よりも高額になることを決意の上でお取組みください。もちろん、それも自己責任の上です。決してお勧めしている訳ではありません。
鎮座する新生つきまろッド&うきまろリール
一先ず完成というところです。それにしても、バカみたいに時間と手間暇をかけてしまいました。「一体なんの意味があるのでしょうか?」と突っ込みたくもなりましたが、今さらです。後には引けなくなった結果とも言えなくもないです。
生まれ変わった月まろ
その雄姿?は、月の称号に相応しいものなのだろうか?
既に古老と化して眠る寸前の富士パーツと、コルクのリールシートナットを再び呼び起こしてみる。
世界の富士工業製パーツが大半を占めるようになる。
ジッタースティックとつきまろと月竿(1063-F1p-UM-Armor)
姉妹血縁といったところか
無事完成しましたということでそれでは次へと・・・・夏の最中の夕方実践にはいりたいと思っています。この夏のターゲットと言えば・・・・ですが、そう手軽にかつ大胆に行える場所や条件は、あまり多くはないようです。
相棒は、元祖ノイジーと言っても過言ではありません。やはり完成形なのでしょうかこの基本を超えるものは無さそうです。それはまさに、架空の甲虫です。それを使いましょうか。いや使うしかないといったところでしょうか。使います。不滅のあれを。
どこまでいってもそれは、架空の甲虫なのですが。
つきまろでんせつ うきまろのゆめ-7 ― 2020年11月16日 17:18
コロナ感染拡大も少し勢いが増して来たようです。
先日、お茶うけに食した吉原殿中です。水戸藩由来ですが、感じは五家宝に似ています。
地味に美味しいです。
実践投入
うきまろッド突撃
実践投入前:上と戦い抜いたその後:下
もう二度と販売される事はないと思われるjapan specialのウキ色だが、是非復刻を願いたい。夕マズメにはケミホタル無でも良く見えるのはとてもありがたい。この釣りには、視認性が最も重要な要素の一つでもある。
隠れた名品カラー?
だと思うのだが既にそれは生産されていない
その威力とは?
うきまろリールオリジナルとのコンボ
ひと昔前の夏の釣と言えば、ズバリ私の中では、シイラです。そうあのシイラです。時々マヒマヒとか言われてグルメ番組に出てくる?あのシイラです。しかしながら、どちらかというと海外の方が人気なのかもしれません。釣関係のアパレルでも良く見かけます。外洋では、非常にポピュラーなおさかなです。
もうかなり前のことになりますが、沖釣りと呼ばれている一般の船釣りではあまり評価が良くなかったのを覚えています。むしろ、邪気に扱われているのをこの目で何度も見てきました。それは、ぺんぺんと言われる80㎝くらいまでのものから、130㎝くらいある大型に入る立派なおでこのオスシイラであっても、その綺麗な体色とは裏腹に、適当に扱われていました。彼らのほとんどは、捨てていました。リリースという名の捨てる感じでした。なんとも不本意な評価でしょうか。地方によってマンビカとかマンビキとかトウヤクとか言われています。一説によると、昔は死体の下によくついていたとか言うことで、シビトクイとも言われていたそうですが、実際は死肉を食べることはありません。どちらかというと他の掃除屋さんが食べていると思います。その昔、私の父が申すには、巡洋艦(駆逐艦?そこが定かではありません。今度墓参り時に調べておきます)が撃沈されたあと、浜に遺体が上げられた際、その遺体の中から、アナゴが出てきて以来アナゴが食えないと言っていました。大のアナゴ好きな私が小学校低学年の頃よく聞かされました。父にとっては、先の大戦時には、既に小学生でありました。その時代は、まだ戦後30年といった頃の時代ですから、多くの戦争体験者の方々でした。もちろん、私の祖母も母も物凄い空襲の毎日を生きてきた人達でした。
大型雄のシイラ14.5㎏
2007年7月の駿河湾での釣果
バンブーロッド(竹竿)フライで上げる(吉田氏)
この時、セットされていたリール=フルーガーメダリストは破壊されてしまった。船で追ってキャッチできたが楽しい時間だったがまたまた残念ながら、その画像が消失してしまった。
話を元に戻します。
それが、ルアーフライと言った、疑似餌釣り系になるとその評価は一転しました。ルアーで釣るシイラの映像が、釣番組で出てくるようになりました。ルアーに襲い掛かるシイラの勇猛ぶりや、その海の中を全力で疾走しては、大きく飛び上がる有様は、とても刺激的でかっこよいものに見えました。まさにマンリキ、マンビキです。そのうち夏ともなれば、専用の船もあり、現在でもとても人気の釣です。もちろんシイラ釣りは、私も好きな釣りの一つです。そんな夏のシイラ釣りも何年も行っていない気がします。あの10㎏を超えてくるとそのパワフルな引きは、マンビキ、トウヤクの名に相応しいものです。
さて、シイラの話はこれで最後にしたいと思いますがいつの日かまだ釣ったことがない20㎏以上が釣れたなら、一度シイラだけで何か執筆したと思います。今年もコロナ禍でなければ、このタックルでシイラに挑むことを企んでいました。悪い大人の企てです。それはうきまろリールの破壊を想像してしまいます。あのかわいいキャラの目が笑顔のまま破壊されそうです。その前に彼の誇らしいダイヤルドラグが先に破壊されるかもしれません。
あるいは、そのうきまろラインが一瞬にしてはじけ飛ぶかもしれません。そんな想像をしながら、改造するのはとても楽しい感じです。悪い大人です。
それでも、ロッドのパワーと構成、そして富士工業社が誇るガイドリング素材のSICリング搭載なら、10㎏を超えるシイラとのやり取りも問題ないない?かなあと思いましたが、リールはその攻撃に耐えられるかかなり不安があります。もし耐えたとしても、その糸巻き量は、たったの75mしかありません。それはかなり危険です。できるだけ10m以内で掛けたいものです。それでもラインはすべて出されてしまうか、途中の摩擦に耐えきれなくて切れてしまうかもしれません。なにせあのこころ細いピン1本で支えてあり、そこには熱が発生するからです。そこを、ある程度のリールに換えて使うことも考えてみましたが、それなら獲れる自信がありますので、とりあえず却下としました。
いずれにせよ、日ごろお世話になっている船長が沖へ連れて行ってくれなければなりませんので、この夏は諦めるしかありません。そんな2020年の夏です。本当なら、東京オリンピックで盛況の夏です。それも、幻影でしかないようです。なんだかすべてが幻影であったり、幻だったりしてきました。憂鬱な暑い夏です。暑さだけがリアルです。あとはすべて幻、幻影に見えてきました。
幻影と戦う、つきまろッドコンボ
軒並み先輩を踏み台にするつきまろとうきまろ
その笑顔のリールが、幻影では破壊されてしまうのかもしれないが下剋上を狙う
つきまろでんせつ うきまろのゆめ―8 ― 2020年11月20日 17:04
折角だからと、近くでなんとかなりそうなターゲットとしては、やはり暗闇の忍者であるヤツ・・しかいないとしました。つきまろの相棒は、元祖ノイジーである彼、そうジッターバグです。その歴史については、ここでは省略しますが、このルアーは、先の大戦前に完成しています。これは、我々日本人にとっては到底考えられない次元です。それだけアメリカと言う国は当時からとても豊かだったと思わせられます。しかもそれが、現在も販売されているということは、更に脅威です。現在その会社は、オリジナルではありませんが、会社名や商品名であるジッターバグは未だ現役です。私は、ナマズ釣りに於いてほぼこのルアーとそのファミリーしか使っていません。それだけ信頼している疑似餌です。現在日本には、その疑似餌を参考に基本から改良されてとても良いルアーが多く存在していますが、やはりコレ=元祖に尽きます。それだけ名品だと思います。
そのジッターバグの中でも視認性がとても良いウキ色のカラーを選択します。サイズはスタンダードの5/8ozやはりこれでしょう。そのルアーに決まりました。
次に、ラインつまり道糸はどうするか?ということですが、この際ですからとりあえずリールに既に巻いてあるオリジナル3号という糸を使うことにしました。ある意味冒険ですが、最初から日本製高品質ラインを使うのもなんだな~というノリです。そこは、オリジナルで勝負してみましょう。ラインは何処製とも記載されていませんが、恐らく大陸製ではないでしょうか。ラインが少し不安ではありますが、そこはやはり変更無でいきましょう。
ご丁寧に基本中の基本から図示されている
とても解り易い
さて他のギアは、フル装備で抜かりはありません。しかしながらやる気モードをなんとも緩くするリールにある顔をみると力はぬけそうになります。人目を気にするととても恥ずかしくもなりますが、そんなことを気にしていても仕方がありません。むしろ、息吹でそれをカバーできないものでしょうか。
いっそのこと、千葉先生が、もってTVCMか動画配信して欲しいものです。またそれは、本郷猛先生でもいいかもしれません。
いつもの場所では、人は居ても釣りに関心のある人にはまず出会いません。時々軽トラで来られる犬の散歩に来られる初老のおばさんかおじいさんくらいです。またある時は、私の目の前をダッシュして横切る、キョンにも出くわしました。またそれが、川をゆっくりと泳いで行く姿もみました。こいつは水陸両用なのかとおもいました。まあ野生動物には予め備わった運動能力なのでしょう。大陸から連れてこられても、この繁殖力はもの凄いものです。もちろん今害獣として駆除対象に入っている動物なのですが、彼らも意図的に連れてこられた生き物です。人間というものはなんとも都合の良いものですね。今では、厄介者、外来生物と化しています。彼らの言い分があるとしたら、勝手に連れて来て、勝手に処分かよ!だと思います。きっと。ちなみにキョンの肉は大変美味しいらしいです。私は、食べたことはありませんが。これだけキョンだらけだと駆除後の利用法もあってもよいのかと思います。(一部で利用されているらしいですが)
そんないつも場所で、まず投げてみることにしました。プッシュボタンを押して投げる瞬間に、それを離すと糸が出て行く仕組みです。これも基本から解説図示されていることに、これが低迷する釣りというレジャー、スポーツの復興を願う思いが込められていると思うのは、私だけでしょうか。あとは、あのリリースする瞬間のコツを掴めばあなたのお子さんも立派なキャスターです。私もなんだか初めてスピンキャストリールで投げてみた1970年代へタイムスリップしそうです。わくわくして投げたこと、投げ竿でトライしたこと、当時ダイワ精工がフルラインナップしたシルバーキャスト、ゴールドキャストが発売されて、店に並んでいたこと。一体どんな人が買って使うのだろうかと思ったものです。今は、もう存在していない呉のささき釣具で買ったあのシルバーキャストミニもまだ実家に転がっていたのを思いだしました。40年以上も前の話ですが夢がまたふつふつと湧いて来そうです。その時代にバックしてしまいそうになります。今は2020年ですよ。当時のささきつりぐは、あまりにも忙しくて、中に入ることすれままならない時代でした。多忙に多忙で家族総出できりもみされていた頃、昭和50年代のことです。
ついつい夢が拡がる
ZEBCO 202
こちらは、シルバーキャスト以前のダイワファントム200
箱にはファントンと書いてあったように思う
つきまろでんせつ うきまろのゆめ‐9 ― 2020年11月22日 17:54
これが、密なのかどうなのか私には判りませんが。
そんな、現状ですが、いったいどうなっていくのでしょうか。先は誰も判りません。
なんとも今からは考えられないことが書いてある
こうなるには、諸事情があったことだろう
カバーを外したところ
この頃は、まだ大口フロンドカバーは採用されていない
フロントカバーは、マチックの匂いがするが
現実は、古いグリスの匂いしかしない
後方のプッシュボタンを押したところ
この位置でラインがひっかからないようにしている
ギアボックスギリギリのメインギア
基本構造は、この頃からほぼ同じだが、ボックスギリギリギアである。
アルミダイキャスト製とはいえ、なかなかの重量感である
少年がかつて抱いた夢は、舶来品の中に存在していたように思える
アメリカ製の刻印がきっかりとその堂々たる場所に
恐らく、スピンキャストリールの大口フロントカバーという大口径のフロントカバーの製品を発売したのはダイワ精工ではないかと思います。当時王道中の王道と呼ばれるZEBCO社には、採用されていませんでした。もちろんあの名品ABU社にも採用されていませんでした。(それは505系のアンダースピンというタイプのリールとは違います。)
それぞれ、フロントカバーのライン放出口の大きさが違う
理屈から言うとダイワ精工が一番大きいのだが、なぜこれを他社が採用していないのかは定かではない。キャスティングコントロールと言う点を主眼に置くと、大口にはならないという意見もあるが。
このうきまろリールは、その内径が多少大き目になっています。またこの部分だけステンレスを採用しているように思われます。それが功を期したかどうかは何ともいえませんが、思ったより良くルアーが飛んで行きます。もちろんロッドにSIC リングを搭載したガイドということが影響しているのは間違いありませんが、それにしてもセットもんのおもちゃに近いリールであっても、釣りになる飛距離が出るということは、私の想像以上です。また、錘の適合値まで記されていて、丁度5/8ozの約18gは、竿にきっちりと乗ってきてとても投げやすいです。適度な硬さです。狭いポイントもきっちりと投げることが可能です。なかなか優秀な竿になりました。この釣りに関しては、そう高速で巻くことはしないので、いつもどおりアクションも可能です。リールとブランクは及第点と思います。
着水後。
竿先をツンツンと揺らすと疑似餌はお尻を振っている様子です。なかなか軽快、とまではいきませんが、問題のない釣りができていることに少しの安心感も出てきました。ただし、河川の本流、支流での上流に投げて、下流に引いてくるというスタンダードなコースは少し苦手なようです。全くリールが追いつきません。ここは流れを横切らせるクロスキャストというパターンか、流れに逆らってルアーを操作するダウンクロスキャストに絞り込んでの釣になります。河川では単純な流れだけではなく、反転流やその流れ方や落差、支流との合流によって案外複雑なものです。魚は基本的に正の走流性をキープしているもので、流れに対して頭を向けています。そういう意味でもダウンクロスキャストから逆引きというパターンは、極自然な餌の流れとはいかないと思います。ただし、遊泳力を持った餌が流れに逆らってそれこそ姿勢をキープしているのをしばしば目撃するかもしれません。そのイメージで疑似餌を動かしてみるとドンピシャな場合も多々あり、あなたやあなたのお子さんと感動を得ることになるかもしれません。いやきっと感動を得る事ができるでしょう。私が子供だった時と同じように。このコンタクトの瞬間は、きっとあなたのお子さんを魅了することでしょう。
単独釣行というのは、子供の頃からあまり好きではないものの、一人で夕方の1時間程度の遊びではそうなりがちです。それは、自分の都合だけというメリットを生かすとなれば必然になってきます。よって、ヒットした瞬間を多角度から撮影してくれる人はいませんので、その様子の画像がないのが少しだけ?残念でもあります。それも致し方ないところです。
キャストを繰り返すと、ダウンクロスでコースを通すとバン!と水飛沫を上げてヤツが出てきました。いつもそれは、ハラハラ、ドキドキです。生命感があり、そこに間違いなく、対象魚がいることがわかります。集中力も加算されていきますが、リールの表情は、常に笑顔で気が抜けそうです。疑似餌は、ポコポコという心地よいサウンドを放ちながら、いつものスピードで巻いてきます。やはりこのリールでは多少忙しくなります。最も忙しくなるのは、回収時です。かなりの高速で巻き上げるつもりでハンドルをくるくると素早く巻いても、その元々のギア比がかなり低速なので案外手元は、忙しいものです。テニス肘を患う私にはあまり良くありません。
数度程同じところへ投げて同じコースを引いてきますが、もうヤツは出てきません。残念ではありますが、それは良くあることです。反応がないので、諦めて、少し移動します。
移動後、同じくダウンクロスキャストで誘いを入れていきます。一投目で反応がありました。水面がざわついて動きます。ヤツです。すかさず回収して、もう一度そこに投げています。疑似餌は、良いところに落ちました。そこで竿先を操作して動きを与えます。出てきました。今度は、追ってきます。しかし、針がかりしません。
大きく息を吐いて、少し間を置いてから再びキャストします。ここはオートいぶきです。
今度も良いところへ落ちました。アクションをかけていきます。小さく波紋がでました。“頼む、かかってくれ”という気持ちとは裏腹に、彼はもう水面を割って出てくることはありませんでした。この釣りは、そんなことも多いです。
気を持ち直して移動することにします。